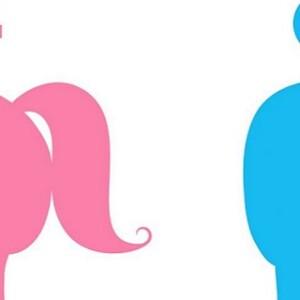出生前診断は胎児の健康状態を早期に知る手段である一方、命の選別や中絶に関する倫理的な問題が存在します。
とくに、中絶が許容される時期に診断が行われるため命の選択に関する議論が多く、検査自体に倫理的な葛藤を抱える人も少なくありません。
胎児に異常が見つかった場合に中絶を選ぶべきかどうか、出生前診断に対するさまざまな意見を考慮しながら慎重に判断したいと考える人もいるでしょう。
この記事では、出生前診断に関する倫理的問題を日本そして海外の状況とともに詳しく解説します。さらに、実際に診断を受けた人の意見や診断結果が陽性だった場合の中絶率についても紹介します。
出生前診断の目的
出生前診断の基本的な目的は、胎児の健康状態を正確に把握し家族が適切な意思決定をするための支援です。
疾患に応じた適切な医療施設の選択や出生後の支援体制を整えることで、妊婦の不安を軽減し、出産できる体制を構築することも目的としています。
出生前診断は、新型出生前診断(NIPT)や羊水検査などさまざまな方法を用いて妊娠中に胎児の染色体異常や先天的な疾患を確認できます。
出生前診断により早い時期に胎児の疾患の有無を把握できることから、子宮内での治療や出生後の早期治療が可能です。
このように、出生前診断は単なる検査ではなく、妊娠・出産・育児に関わる包括的な支援の一環として提供されています。
参照:厚生労働省「NIPT 等の出生前検査に関する情報提供及び施設(医療機関・検査分析機関)認証の指針」
参照:厚生労働省「NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会報告書」
出生前診断の倫理的問題とは

出生前診断には、以下のような倫理的問題および社会的課題が存在します。
・命の選別にあたる問題
・母体保護法による問題
出生前診断は、大きく分けて「非確定検査(スクリーニング検査)」と「確定検査」の2種類です。なかでも新型出生前診断(NIPT)は、母体への負担が少ない方法で高精度な検査が受けられることから、多くの議論が交わされています。日本国内で2013年に導入された新型出生前診断(NIPT)は、非確定検査のうちのひとつです。
命の選別にあたる問題
出生前診断には、命の選別に関わる倫理的問題および社会的課題が存在します。
新型出生前診断(NIPT)の普及により、染色体異常や先天的な障害をもつ子どもに対する偏見や安易な中絶を助長する恐れがあるためです。
日本ダウン症協会は、新型出生前診断が一般化することに反対し、障害者と共存できる社会の構築が必要だと訴えています。
実際に、ダウン症やエドワーズ症候群などの染色体異常は誰にでも起こりうる疾患です。どのような障害や疾患があっても、大切に育てるべきとの声も多く存在します。
そのため診断を受けた妊婦は、社会的価値観や医師の助言などさまざまな要因に影響されながら、命の価値について難しい選択を迫られます。
検査精度が向上し受検が容易になったことで、新型出生前診断(NIPT)など出生前診断を受ける人が増加していますが、同時に倫理的問題に直面する人も増えているのが現状です。
このような状況を受け、厚生労働省は2020年に「NIPT等の出生前検査に関する専門委員会」を設置し、現在も議論を重ねています。
参照:日本ダウン症協会「出生前(しゅっしょうまえ)検査について」
参照:厚生労働省「NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会報告書」
母体保護法による問題

出生前診断の結果にもとづいて中絶する場合、母体保護法がどのように適用されるかも問題点です。
母体保護法は妊婦の健康の保護を目的としていますが、出生前診断の結果にもとづく中絶についての明確な規定は設けられていません。
母体保護法では、「身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害する恐れがある場合」に該当する場合、人工妊娠中絶が認められています。
出生前診断によって確認された胎児の異常が条件に該当するかは、法的・倫理的な判断に関する解釈がさまざまで、明確な基準はないのが現状です。
妊婦は、胎児に異常が見つかった場合、適切な医療施設を選び疾患を受け入れて出産の決断を下す権利をもっています。しかし、出生前診断で陽性と判断された後に、妊娠中断の判断が高い割合で行われていることも事実です。
参照:日本産婦人科医会「母体保護法」
参照:厚生労働省「NIPT 等の出生前検査に関する専門委員会報告書」
出生前診断陽性者の中絶率
新型出生前診断で陽性と判断された場合、9割近い妊婦が中絶を選択しています。
新型出生前診断の受検者を対象としたアンケートによる、染色体異常別の中絶率は以下の通りです。
・21トリソミー(ダウン症候群) 87.5%
・18トリソミー(エドワーズ症候群) 60.3%
・13トリソミー(パトウ症候群) 69.0%
上記の中絶率は、偽陽性者やIUFD(子宮内胎児死亡)となった人などの数も含まれています。
たとえば21トリソミーの場合、陽性者数の943名のうち以下を差し引いた人数が実質的な中絶率を割り出す数と計算できます。
・偽陽性:24名
・子宮内胎児死亡(IUFD):81名
・研究脱落(中絶実施の確認が不可):34名
これらの人数を差し引いた804名のうち774名が妊娠を中断しているため、中絶率は96.3%と捉えることもできるでしょう。
中絶を選ぶ理由には各家庭が抱える事情や社会の受け入れ態勢など、さまざまな要素が絡んでいます。それぞれの選択には深い背景や理由があるため、安易に評価することはできません。
参照:厚生労働省「NIPT受検者のアンケート調査の結果について」
出生前診断を受検した人のレポート
出生前診断を受けた人の感想には、ネガティブな意見とポジティブな意見が混在しています。
たとえ結果が陰性だったとしても、検査を受けること自体にさまざまな感情が引き起こされるため、簡単には割り切れない問題です。
実際に検査を受けた人の意見を詳しく見ていきましょう。
ネガティブな意見
出生前診断を実際に受けた人のネガティブな意見として、以下が寄せられています。
・命の選択をしてしまった気がした
・罪悪感がある
・今でも検査を受けてよかったのか自問している
・陽性だったら苦しんだと思う
・結果を知って混乱した
・子どもの疾患の深刻さやその後の見通しが不明確なことに戸惑った
ネガティブな意見に共通するのは、「どのような子どもであっても愛するべきではないか」と自分に対して罪悪感を抱く点です。「もし陽性だったら産んでいなかったかもしれない」と思い返すことで、さらに罪悪感が強まることもあります。
ネガティブな意見から、出生前診断を受検したことが心に大きな負担をかけることがわかります。
参照:厚生労働省「NIPT受検者のアンケート調査の結果について」
参照:京都大学「出生前診断をうけて親になる経験:G さんの語り」
ポジティブな意見
出生前診断を実際に受けた人のポジティブな意見としては、以下が寄せられています。
・妊娠を継続する場合に心の準備や産後の動きなどを勉強できてよかった
・不安な気持ちでいるより、結果がわかってよかった
・受検をきっかけに夫婦で話し合い、絆が深まった
・子どもの障害へのサポートを事前に準備できてよかった
・一人目が先天性疾患で死産だったため検査で異常がないとわかり安心して出産に臨めた
・検査結果が妊娠中の精神的な支えとなった
ポジティブな意見からは、検査が不安の解消をもたらし、家族とのコミュニケーションを深める契機になったことがうかがえます。
ただし、検査自体が心理的負担を与えることから、結果が陰性であっても検査後のメンタルケアを必要とする人も少なくありません。
参照:厚生労働省「NIPT受検者のアンケート調査の結果について」
参照:厚生労働省「出生前診断をめぐる女性・パートナーの体験について」
各国における出生前診断の倫理的問題

出生前診断には、国ごとに異なる倫理的な問題が存在します。
たとえば、アメリカではプライバシー権にもとづき女性の意思で中絶を決断できますが、受精卵を生命とみなす保守的な意見も根強く残っています。
また、中絶に関する法律は州ごとに異なり、一部の州では中絶が認められていません。
一方でアメリカは障害児に対する社会的支援が充実している点が特徴です。そのため、陽性と診断された場合の中絶率は約60%とされています。
イギリスは新型出生前診断(NIPT)と確定検査が無料で提供され、多くの妊婦が出生前診断を受けている国です。胎児に異常が確認された場合は、複数の医師の判断があれば出産直前でも中絶が可能で、費用も国が負担します。
ただし、法的・経済的サポートが充実している反面、障害に対する否定的な態度を助長しているとの批判も少なくありません。
このように、各国の法律やサポート体制の違いは妊婦や家族に大きな影響を与え、出産に関わる決断にも深く関わっています。
出生前診断の倫理的問題をサポートする遺伝カウンセリングの重要性

妊婦の不安やストレスを和らげるために、出生前診断には遺伝カウンセリングの存在が欠かせません。
遺伝カウンセリングは、正確な遺伝情報や社会の支援体制などをわかりやすく提供し、検査を受けた人や家族のサポートを目的としています。
具体的には、以下のような相談が可能です。
・遺伝に関する悩み
・出生前診断の検査内容
・社会的な支援体制
・出生前診断における倫理的な問題
出生前診断は、妊婦にとって大きな心理的負担を伴う検査です。適切なサポートがない場合、誤った判断を下したり決断が難しいと感じたりするでしょう。
遺伝カウンセリングは、自分の気持ちと向き合いながらよりよい選択をする手助けとなります。また、検査の理解を深めることで情報不足による誤解を防ぎ、納得して検査を受けることにもつながります。
単に医学的な情報の提供のみでなく、心理・社会的なサポートをすることも特徴です。
出産に伴う不安を軽減し、自らの力で問題を解決するために遺伝カウンセリングは不可欠といえます。
出生前診断の倫理的問題には継続した議論が必要
出生前診断の倫理的な問題は非常に複雑で、簡単には答えが出ない課題です。今後もこの問題については、さまざまな視点から議論が続けられるでしょう。
また、出生前診断は受ける前も受けた後も精神的負担が伴います。出生前診断における精神的負担を軽減するためには、遺伝カウンセリングが重要です。
平石クリニックでは、母体の血液採取により胎児の染色体異常を確認できる新型出生前診断(NIPT)を妊娠6週目から受けられます。認定遺伝カウンセラーが在籍しており、検査前の疑問や不安を無料で電話相談可能です。妊婦やご家族が納得のいく選択や決断をするために、ぜひご相談ください。